皆さんこんにちは、会計士Dです。
今回の投稿テーマは、初めてとなりますが、雑記をテーマに、書籍:業界地図についてお伝えしたいと思います。
これまでの資産運用や公認会計士に関連する投稿と少し変わりますが、会計士Dが、日々利用しているもの、日常生活で感じること・考えること・思うことなどについても、雑記ブログとして投稿していきますので、宜しくお願い致します。
今回は、会計士Dが、業界地図をどのような場面で利用しているのか、業界地図の良いところなど、お伝えしたいと思います。
- 業界地図がどんな書籍か知りたい方
- 業界地図がどのような場面で役に立つか知りたい方
- 就職活動、転職活動を考えている方
業界地図
先ずは、業界地図がどのようなものか、お伝えします。
業界地図は、書籍(本)です。
そして、読んで字の通りですが、様々な業界(例えば、自動車業界、半導体業界、ホテル業界など)の主要なプレイヤー、つまり、大手企業が、地図のように1ページ毎にまとめられています。
業界地図に記載されている企業は、各業界の主要プレイヤーです。そのため、掲載されている企業は基本的に上場企業や、非上場でも規模の大きい企業、に限られています。
また、基本的には各業界の主要な日本企業がピックアップされています。
世界的に注目が集まっている業界については、海外企業の情報も豊富な場合がありますが、基本は日本企業の業界主要プレイヤーが、ピックアップされている印象です。
代表的な業界地図
書籍のイメージが具体的に湧かないという方がいらっしゃいましたら、下記に2つの代表的な書籍を記載してます。
書籍名をクリックして頂くと、Amazonの画面に進みます。そして、当該画面を下にスクロールしていただくと、書籍の見方が解説されていますので、ご興味のある方はご確認頂ければ幸いです。
有名な業界地図の書籍は、以下2つです。
現在、どちらの業界地図も、2021年版が最新版として販売されています。
今回の投稿では、上記2書籍の比較はしませんが、会計士Dは日本経済新聞社(以下、日経)の日経業界地図を購入しました。
日経の業界地図を購入した理由は、会計士Dの勤め先に東洋経済新報社(以下、東洋経済)の業界地図が置いてあるので、今回は日経の業界地図を購入した次第です。この他に特に深い理由はありません。
業界地図を利用する場面
続いて、会計士Dが業界地図を実際に利用する場面に関して、ビジネスとプライベートに分けてお伝えします。
ビジネスで利用する場面
会計士Dは現在、M&A関連のコンサルティング会社で働いてます。
例えば、クライアントのM&Aターゲット企業を選定するにあたり、先ずはターゲット企業が属する業界の見通しや主要なプレイヤーを把握するために、業界地図を確認します。
或いは、初めてお会いする企業に関して、業界内での立ち位置、競合他社の動向、業界トピックなど、事前に情報収集するために、業界地図を活用したりします。
上記のように、要は企業の属する業界の概要について把握するために、業界地図を日々の仕事で活用しています。
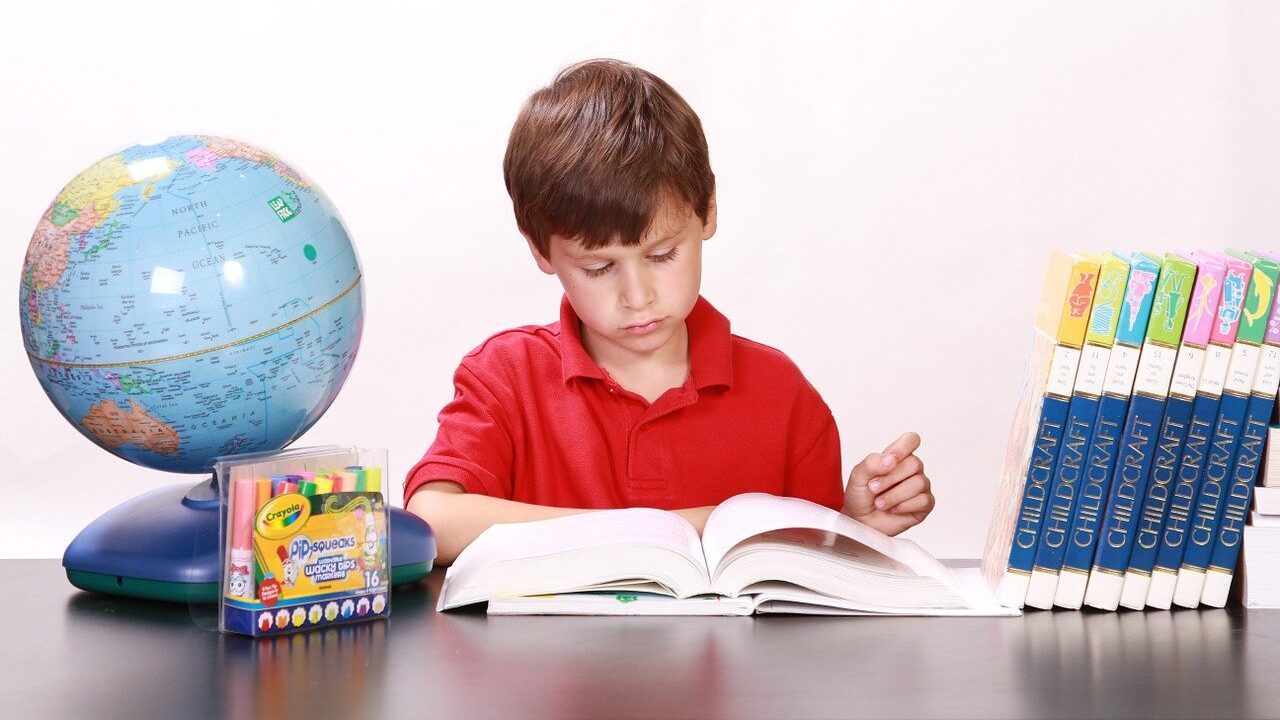
プライベートで利用する場面
プライベートでも業界地図を見たりします(変態ですかね。。笑)
例えば、情報番組を見ている時です。
会計士Dは、テレビ東京で放送されている、”WBS(ワールドビジネスサテライト)”、”ガイアの夜明け”、”カンブリア宮殿”について、仕事が忙しくなければ、ほぼ毎日・毎週見ています。この3つの情報番組は会計士Dが大好きな番組です。
番組を見ている中で、気になった業界や企業がトピックとなった場合に、業界地図をパラパラめくったりします。
テレビ番組でも放映されるような、注目の集まる業界や企業について、業界地図を見れば短時間で概要が把握できるので、このようなプライベートの場面でも重宝してます。

その他、活用出来そうな場面
これは、会計士Dが実際に活用していた場面ではないのですが、例えば日経の業界地図には、企業の初任給も記載されていました。
就活をする学生にとっては、主要な企業の初任給がパッと分かることも良いですよね。
また、転職を検討している方にとっても、検討対象となっている企業が属する業界の主要なプレイヤーを把握しておくことも、検討対象企業の立ち位置や、競合他社の動向が把握できて良いのではないかと考えます。
業界地図のメリット
最後に、会計士Dの個人的な見解となりますが、業界地図の良いなと思うところについて、お伝えします。
短時間で業界・主要企業の概要が把握できる
たった1ページで、文字だけじゃなく視覚的に、業界や主要プレイヤーが把握できるため、短時間で概要を把握出来ます。
地図のように視覚的にも把握できるので、概要把握の観点では、業界地図の活用はとても効率的で効果的と考えております。
値段が比較的安い
業界地図の値段は、東洋経済も日経も1,500円弱で購入できますので、書籍の中では比較的お手頃な値段ではないかと考えます。
そして、業界の数も、180弱ありますので、1冊持っているだけで主要な業界の概要を把握には十分です。
コスパがとても良いと思います。
会話の引き出しが増える
特に仕事をしているときに、業界地図を読んでいて良かったと感じる場面が、自分自身の会話の引き出しが増えることです。
特定の業界の話になったとき、業界の見通しや主要なプレイヤーについて知っているだけでも、会話のネタを自分から提供することができます。
初めて訪問するお客様とお話をするときは、お客様のことだけでなく、お客様の属する業界や競合企業、関連業界や注目を集める業界など知っていれば、話のタネとなります。
話の流れで自然と話題を提供することで、お客様に自分自身を印象付けることができます。

終わりに
今回は初めてでしたが、雑記ブログとして、業界地図について書いてみました。
会計士Dは個別株が出来ない(個別株をすると仕事上とても面倒なことになる)ので、本文には書きませんでしたが、個別株をしている方々はご自身の興味ある業界を調べる手段として、業界地図も良いかもしれないですよね。
業界地図について、気になる点など他にありましたら、ご質問いただけますと幸いです。
また、こんなテーマについて記載してほしいなど要望がありましたら、可能な範囲でブログで投稿してみたいと思いますので、リクエスト頂けますと幸いです。
以上となります。ありがとうございました。
会計士D



コメント